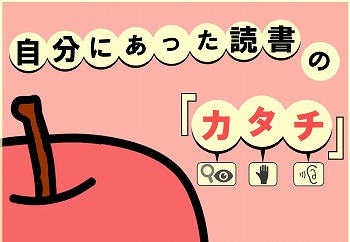本を読む楽しさは、すべての人にひらかれたものですが、目が見えにくい、文字を読むのが苦手、ページがめくれないなど、さまざまな理由で、活字の本が読みにくい人もいます。図書館には、大きな文字の本、やさしい言葉と絵や写真の本、音で聴く本、点字の本など、いろいろな形の資料があります。
今回の展示では、そうした「読みにくさ」を支える資料の一部を紹介します。
成田市立図書館では、こうした資料をいつでも手に取れるよう、「りんごの棚」というコーナーにまとめています。ぜひ、あなたの読書の<カタチ>に合った一冊を見つけてみてください。